|
|||||||||||
奈良県吉野郡天川村に在り、日本で唯一女人禁制の御山です。 又、大峯山とは、山上ヶ岳、稲村岳、大普賢岳、弥山(みせん)、八経ヶ岳、釈迦ヶ岳、行者還岳などを含む大峯山系の山々の総称でありますが、 一般的に大峯山(おおみねざん)は山上ヶ岳(1719m)を示しています。 その山頂には大峯山寺(奈良県吉野郡天川村大字洞川494)が在ります。 大峯山寺本堂は、わが国の高所最大の木造建築物で、国の重要文化財です 山上ヶ岳は修験道の祖・役行者(えんのぎょうじゃ)が開いたといわれている我が国修験道発祥の地であります。 頂上にある大峯山寺は修験道の根本道場であり、ご本尊は蔵王権現。現在でも5〜9月にかけて山入が行われ、数多くの行者が集まる。 1936年 「吉野熊野国立公園」に指定 2004年07 ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録 |
|||||||||||
大峯奥駆道(おおみねおくがけみち) 吉野山から大峯山系を経て熊野の熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)に至る約80kmの道を「大峯奥駈道」(おおみねおくがけみち)と言い、修験者の修行の道となっています。 吉野山から大峯山系を経て熊野の熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)に至る約80kmの道を「大峯奥駈道」(おおみねおくがけみち)と言い、修験者の修行の道となっています。大峯奥駆道が開かれたのは長久年間(1040〜1044)に修験者の義叡、長円により熊野から大峯へと開かれたと言われています。 伝統的な山伏は、この奥駆け全行程を、75箇所([靡]なびき)の行場を巡礼しながら2週間ほどで歩いたといわれます。 奥駆け修行の行場の第一番は熊野本宮にあって、熊野から辿るのを順峰といい、第75番の吉野神宮から辿るのを逆峰といいます。 その昔は天台宗系聖護院(本山派)は熊野から吉野への順峯、真言宗系醍醐寺三宝院(当山派)は吉野から熊野への逆峯のコースを主導していたが、現在では大峯の修験道は、当山派の修験本宗が復活したこともあって、大部分が逆峯によって行われている。 、 参照:大峯奥駆道マップ |
|||||||||||
大峯山護持院(おおみねざんごじいん)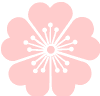 大峯山を護持している御寺で、龍泉寺(洞川)・喜蔵院(吉野)・櫻本坊(吉野)・竹林院(吉野)・ 東南院(吉野)の五ヶ寺を称しています。 大峯山を護持している御寺で、龍泉寺(洞川)・喜蔵院(吉野)・櫻本坊(吉野)・竹林院(吉野)・ 東南院(吉野)の五ヶ寺を称しています。又、大峯山護持院は大峯山行者講社本部として、大峯山の山伏(行者)の得度・先達号授与等、修験道在家信徒の入門の許可等を行います。 |
|||||||||||
| 大峯山l信徒会(おおみねざんしんとかい) 大峯山護持院に先達号及び袈裟法螺等の所持を許可された修験道行者(在家信徒)で構成される。 毎年5月28日には瀧谷不動尊、10月1日には吉野櫻本坊において柴灯大護摩供が櫻本坊院主大導師の元厳修される。 |
|||||||||||
| 大峯山寺阪堺役講(おおみねさんじはんかいやっこう) 高祖神変大菩薩の遺徳を追慕し、大日大聖不動明王・金剛蔵王権現を信仰し、 護持院、吉野区、洞川区、と共に大峯山寺の管理の役割を担うもので、 大峯山の戸開け・戸閉め柴燈大護摩供行事等の役割りを承る講である。 大阪四島の岩・三郷・光明・京橋と、堺四島の鳥毛・井筒・五流・両郷の、 八講をもって大峯山寺阪堺役講と称したものである。 |
|||||||||||
| 女人大峯(にょにんおおみね) 山上ケ岳の西には稲村ケ岳(標高1725m)があります。 女人禁制の大峯山に対し、女人大峯と呼ばれているこの山は、昔から雨乞いの山として名高く、長い間女人の入山を閉ざしてきましたが、戦後になって解禁されました。 特に山頂の大日岳に祀られた大日如来は女性行者の信仰が篤く、普通の登山者だけでなく、信仰登山でもにぎわっています。 山頂付近は高山植物が豊富に見られ、特にシャクナゲの咲く季節は素晴らしい眺めとなります。 参照:稲村ヶ岳登山マップ / 洞川マップ |
|||||||||||
| 大峯山護持院桜本坊大嶺講正大先達澤田 進0728511301 | |||||||||||